鑑定書は、ダイヤモンドのグレードが書かれた証明書です。
ダイヤモンドには4Cと呼ばれる品質評価の基準があって、鑑定書にはその4Cが記載されています。4Cというのは「カット」「カラー」「クラリティ」「キャラット(カラット)」のことで、英語ですべてCから始まるので4Cと呼ばれています。
ダイヤモンドの価値は、4Cを基準に決められるので、鑑定書の存在はとても重要です。もちろん4Cの評価だけで値段が決まるわけではないのですが、カラーやクラリティの評価が1グレード違っただけでも値段が全然違うことがあります。
ところがこの4Cというのはとても曖昧なもので、鑑定機関が違うと評価が異なる場合があるのです。というのもダイヤモンドの評価というのは、人が目で見て判断するんですね。例えば色(カラー)のグレードはマスターストーンという色の見本となる石があって、それと鑑定する石を見比べて評価します。そのため、鑑定機関によって評価が違うどころか、同じ鑑定機関でも鑑定士のAさんとBさんで評価結果が違う、なんていう可能性もあるのです。
もちろん鑑定するたびに評価が違ったり、他の鑑定機関と違ったりしても、評価や価格が安定せず困るので、鑑定機関ではちゃんと一定の評価が出るようにしています。しかし以前、全国宝石学協会という、当時、国内では中央宝石研究所と双璧をなしていた鑑別・鑑定機関が、特定の業者のダイヤモンドの評価を1グレード高くつけていたという事件がありました。これによって業者は、ダイヤモンドを高く販売することができ、不当な利益を得ていたんですね。その結果、全国宝石学協会は倒産に至るのですが、人の目で評価をするということは、こういう事件を生み出すことにつながりかねません。
なのに何で機械ではなく人の目で評価するのかというと、ダイヤモンドの評価には、むしろ曖昧さこそが大事だということなんじゃないかと思います。美しさっていうのは極めて感情的なもので、数値で測ったりプログラムで判断したりすることができません。同じようなインクルージョンがあっても、石によって綺麗に感じられたり、そうは感じられなかったりします。人間には、エラーがあったとしても美しいものは美しいと判断できたり、逆にエラーがなくてもNGが出せる能力があります。だから最終的には人の目で判断しなければならないんじゃないでしょうか。
で、鑑定書には4Cの他に、寸法や蛍光性、その他の情報なども記載されます。業者はこれらの情報とダイヤモンドの相場から判断して、商品の値段を決定します。
鑑定書は決してダイヤモンドの価値そのものを記したものではありませんが、価値を決定づけるのに大きく左右するものです。そのため鑑定機関には正確な情報を記載してもらいたいですし、販売業者は信頼のおける鑑定機関を選んでもらいたいですね。そして購入する際には、できる限り鑑定書か、鑑定書を簡素化したソーティングシートの付いているものを選びましょう。

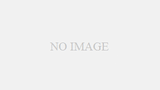
コメント