宝石を評価する際によく使われる用語として「照り」という言葉があります。
これはすごく曖昧な言葉で、明確な定義はなく、つやや光沢、輝き、透明感、色の深みと鮮やかさ、傷のなさなどを総合して、品質の良し悪しをいう便利な言葉です。
とりあえずつやつやでインクルージョンが少なく綺麗だと思ったら、「照りがいいですね」と言っておけば、通ぶることができます。
なので「照り」の意味合いは、プロでも一人一人違うかもしれません。
僕自身、「照り」が何となく分かるようになったのは、真珠が少し分かるようになってからだと思います。
真珠ってその性質上、ピンクとグリーンの光沢が出るんですが、その光沢がバランスよく出ていて初めて「照りが良い」と言われる印象があって、どんなにつやがあって光っていても「照りが良い」とは言われない気がします。つやがあったり光をしっかり反射したり、何となく透明感が感じられたりっていうのは大前提で、その上でピンクとグリーンの光沢が見られる……ピンク寄りの真珠でもグリーンの光沢が見られないとダメだし、ピーコックグリーンや黒真珠でもピンクの光沢が見られないと高く評価されない、ということに気づいたんです。
つまり「照り」というのは、総合力なんだなということが分かりました。
でも本当はこんな曖昧な言葉、使っちゃいけないんじゃないかなーとも思います。「照り」って国語的な意味では、「照ること。特に、つや。光沢。また、晴天」ですよね。色とか傷の有無とかは関係ないはず。なのに宝石の評価では色も傷の有無(というか少なさ)も含まれてしまいます。明確な基準がないんです。
こういう曖昧さが宝石を分かりにくいものにしているような気がするんですよね。
と言いつつ、便利だから使っちゃうんですが……照りが良いとか悪いとか言っておけば、それで何となく通じるから、話が早いですしね。

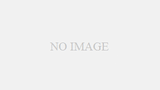
コメント